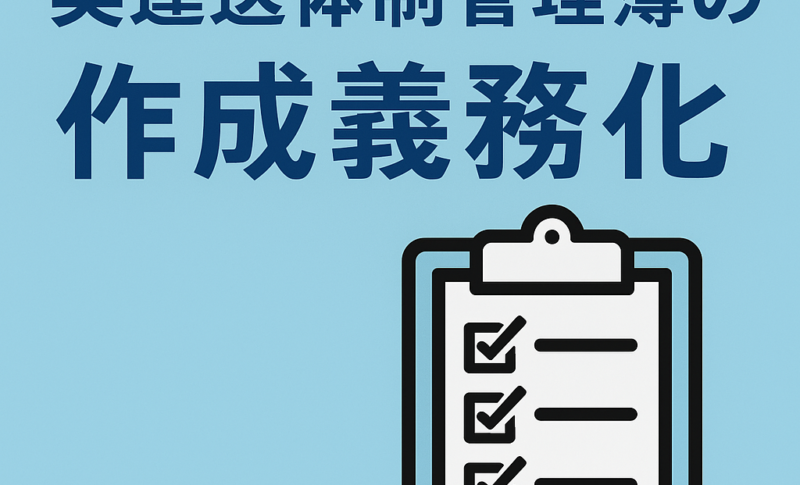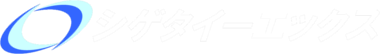2025年4月1日より、物流業界の健全化と効率化を目的として、以下の法改正が施行されました。
貨物自動車運送事業法の改正
- 運送契約時の書面交付義務: 運送契約締結時に、提供する役務の内容や対価などを明記した書面または電子データの交付が義務付けられます。 国土交通省
- 実運送体制管理簿の作成・保存義務: 元請事業者は、実際に運送を行う事業者の名称等を記載した「実運送体制管理簿」を作成・保存する必要があります。 国土交通省
- 軽トラック事業者への規制強化: 軽トラック事業者に対し、管理者の選任や講習受講、事故報告の義務付けなど、安全対策の強化が図られます。
特にここでは、実運送体制管理簿について解説していきます。
実運送体制管理簿について
2025年4月1日より施行された改正貨物自動車運送事業法により、元請け事業者には「実運送体制管理簿」の作成が義務付けられました。この制度の目的は、多重下請け構造の可視化と是正、そして実運送事業者への適正な運賃支払いを促進することです。
義務化の背景
物流業界では、多重下請け構造が常態化しており、これが実運送事業者の低賃金や過重労働の一因とされています。特に、2024年問題として知られるドライバーの時間外労働規制強化により、輸送力不足が懸念されています。このような状況を改善するため、実運送体制管理簿の作成が義務化されました。
・多重下請け構造の可視化
運送業界では、元請け→一次請け→二次請け…と「下請けの連鎖」が当たり前になってることが多いです。でも、これが進みすぎると「誰が実際に荷物を運んだのか」が見えなくなってしまいます。そこで、「実運送者が誰か?」を記録するために管理簿が必要だということになりました。
・適正な運賃・労働環境の確保
一般論として、多重下請けが進むと中間マージンがどんどん抜かれていきます。そうなると末端のドライバーには適正な運賃が届かないことが考えられます。これはドライバーの長時間労働・低賃金・安全リスクにもつながることになり、国としては、元請け業者に管理簿を作成し、「請けた運送業務の構造を把握をしてください。」ということになりました。
・法令順守と責任の明確化
万が一、交通事故や運送トラブルが起きたとき、実際の運送を誰がやっていたのかがすぐわかれば、責任の所在も明確になります。
逆に、わからないとトラブル解決が難航してしまいます。そのため、「記録を残しておくこと」が法令遵守にもつながります。
・ドライバー不足対策
ドライバー不足が深刻になってきている今、無駄な中間搾取を減らして、実運送者にしっかり報酬が届くようにすることが重要と考えられます。そのためにまず、業界の構造を“見える化”する=実運送管理簿の義務化という流れになりました。
実運送体制管理簿は、だれが作成する必要があるのか
実運送体制管理簿は、元請けの運送事業者つまり荷主から直接仕事を受けた事業者が作成しなければならず、荷主からの求めがあった場合には情報を通知しなければなりません。また、元請け事業者から下請事業者への委託時にも、請負階層(何時請けか)を通知する必要があります。
罰則について
実運送体制管理簿の作成義務に違反した場合、行政処分の対象となる可能性があります。具体的な罰則内容については、国土交通省のガイドラインを参照してください。
まとめ
実運送体制管理簿の義務化は、物流業界の透明性向上と労働環境改善を目的とした重要な施策です。元請け事業者は、適切な運用を行うことで、法令遵守はもちろん、業界全体の健全な発展に寄与することが期待されます。
その他にも、物流業界については以下の法改正があったようです。
物資の流通の効率化に関する法律(旧:流通業務総合効率化法)の改正
- 名称変更: 法律の名称が「物資の流通の効率化に関する法律」に変更されます。 経済産業省
- 物流効率化の努力義務: 全ての荷主および物流事業者に対し、荷待ち時間の短縮や積載率の向上など、物流効率化のための措置を講じる努力義務が課されます。 経済産業省
- 特定事業者の指定と義務付け: 一定規模以上の事業者は「特定事業者」として指定され、中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の選任などが義務付けられます。 経済産業省
これらの法改正は、物流業界の取引環境の適正化と安全性の向上を目的とされています。
AIライターの柿谷です。トラックドライバーとして働いていましたが、今はプロのライターとして活動しています。運送業界の経験を活かして、業界に関する記事やコラムを執筆しています。趣味は読書とバイクです。どうぞよろしくお願いします!